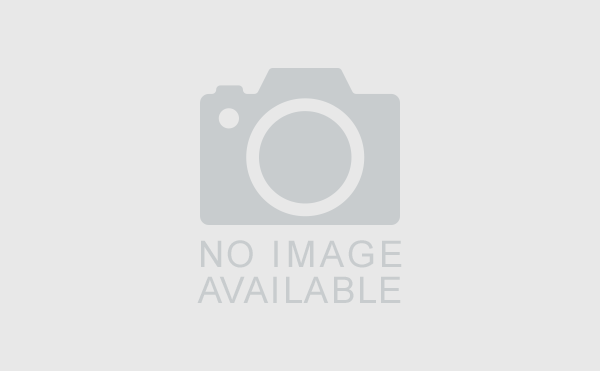CDの2段階仕入れ方法に見るPDCAのチカラとサブスクへの道の起点は顧客視点。

【イニシャル発注】
CDは発売日の約3ヶ月前にメーカーに発注しなければ、発売日に入荷できません。これを「イニシャル発注」(=初期発注)と呼んでいます。この時点では、曲のタイトルすら決まっていないものも多いです。タイアップの予定も正確な情報は少ないです。
○○というアーティストが、○月○日にNEWシングル発売予定です。
または、NEWアルバム発売予定です。
もちろんどんな曲なのか試聴することもできません。ビデオやDVDは、映画やテレビで公開済みなので、音楽CDとは違います。
Q:「聴いたこともない曲を、さて何枚仕入れれば良いのでしょうか?」
この時点では、過去の実績、データを元にどのくらいイケるか予測するしかありません。
予測なんて100%当たるわけがありませんよね。
ですから、このシングルは100枚仕入れても十分に稼げるだろうと予測したら、その70% = 70枚をイニシャルでは発注します。残りの30%は、POSデータで発売後の動きをチェックし、追加発注して、適正枚数になるように調整していくという作戦です。
たかが30%
たかが30%だと思ったかも知れませんが、実際には、データの動向を分析することで30枚追加発注して終わりではなく、50枚、100枚、、、、追加になることもあります。この積み重ねが売上げの大きな差となっていきます。
イニシャル発注時に予測した100%の枚数を発注してしまうと、そこで今月の予算を消化したことになり、発売後のデータを重視しなくなります。中には、予測が外れて、50枚仕入れたのに、20枚で足りたものも、つまり、仕入れに失敗したものも出るので、追加発注に消極的になります。データをチェックしたら、足りないということが分かったとしても、すでに予算を消化してしまっているので追加発注をする余裕がないからです。
追加発注数についても、過去のデータを分析したとは言え、やはり予測なので、イニシャルで失敗すると(仕入れ過剰)追加発注をすることが怖くなってしまいます。そうこうしているうち、適正枚数に調整することなく、時間が経過していきます。
「販売機会ロス」の発生です。
在庫数が足りないということは、お客様から見ると、いつ行っても借りたいCDがない状況になっているということです。
お店の都合(予測)で仕入れている状態と、
VS
お客様のニーズに対応できるように、
「イニシャル」と「追加発注」の2段階仕入れ作戦。
その間、ライバル店は、適正枚数に近づけていきます。お客様のニーズに応えていきます。
イニシャル発注時点から追加発注を予定していた店舗では、最終的に適正枚数にすることができます。今で言うPDCAを週間単位で回してきたのです。(POSデータを毎週月曜日にチェックし、その週末に届くように追加発注をした。)
ネット、Webを活用するときにもこの考え方は大いに応用できます。施策を仕掛けたら、適切なタイミングでデータをチェックしてフォローすることが継続取引の推進に欠かせません。(商品だけでなく、お客様に対してもフォローが大事)サブスクリプションの基礎部分となります。
コロナ禍の現在、そして将来的にも、継続取引、定期購入、サブスク系を強化していく流れになります。
要はアフターフォロー強化の方向のなかで顧客満足度、顧客視点をその中心に据えることが大切になってきます。